
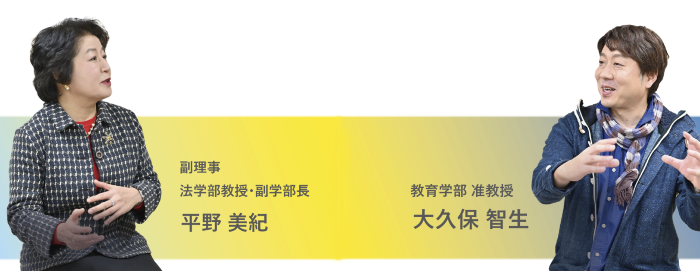
防犯と再犯防止
大久保 平野先生の研究内容を教えてください。
平野 私は刑事法を研究していて、とくに関心をもっているのが犯罪者の処遇。それを犯罪の言い訳にはできませんけれど、多くの場合、犯罪をした人は生きづらさを抱えていることが多いのです。ただ刑罰を科すのではなく、その人が犯罪に至った背景にも目を向け、失敗した人を社会全体で受け入れていくためにはどうしたらいいかを考えています。
大久保 再犯防止活動を行う学生団体PROSの顧問もされていますよね。立ち上げたきっかけは?
平野 <ルールを守らない人が悪いんだから、犯罪者は刑務所に送ればいい>と考えている学生って多いんですね。刑務所から社会に戻ってくることまで考えていないんです。出所者を自分の世界から切り離してしまったら、それで話は終わり。たしかにルールを守らない人もいますが、守れない人だっている。障害があるとか、依存の問題とか、さまざまな理由があります。自分とは価値観の異なる人たちと共存するにはどうしたらいいのかを考えてほしいと思ったのが、PROSを立ち上げたきっかけです。大久保先生は私とは対照的に、犯罪が起きないようにする研究をされていますね。
大久保 私はもともと非行など問題行動の研究をしていて、その流れで万引き防止の研究を香川県警とするようになりました。もう15年以上になります。その成果が大きかったので、次は地域の防犯活動を活性化させる取り組みを行うこととなりました。
平野 それで、香川大学防犯パトロール隊と活動されているのですね。
大久保 そうです。ホットスポットと呼ばれる地域の犯罪が起こりやすい場所をみんなでパトロールしたり、小学校やコミュニティセンターに行って防犯教室を開いたりしています。ほかにも香川県警などと連携し、防犯ウォーキングアプリ「歩いてミイマイ」を開発しました。
犯罪を抑止するもの
大久保 万引き防止と地域の防犯活動に共通してるのは「犯罪機会論」。これは、犯罪の機会を与えないことによって犯罪を未然に防ごうという考え方です。犯人が最も嫌がるのは、人の目。だから人の目をどう作るか、どう増やすかが防犯の観点においては重要になります。よく、万引き防止のために防犯カメラをつけるって言いますけど、あれは防犯じゃないんですよ。防犯カメラは<事後確認カメラ>。犯人は捕まえられるけど、犯罪は抑止できない。犯行を躊躇させ、断念させる状況づくりが必要です。
平野 何か抑止になるものがあることが大切なんですよね。「あの人が悲しむからやめよう」とか。そこは、防犯も再犯防止も同じですね。PROSも、やっているのは生きづらさを抱えた人の居場所と出番作りなんです。出所者って「社会から受け入れてもらえないかもしれない」という不安や孤独を抱えやすいんですが、学生と定期的に会合することで「受け入れてもらえた」「自分はここにいてもいいんだ」と安心感をもてるようになる。それが再犯防止に繋がるんです。
大久保 「やめておこう」と思う気持ちを、どうやって作るかですよね。防犯にはもうひとつ大切なポイントがあって、それはお店の人や地域の人に対して「防犯しましょう」と伝えるのではなく「明るいお店づくりをしましょう」「明るい地域づくりをしましょう」とポジティブに伝えることなんです。「防犯しましょう」と言うと、嫌がる人が多いんですね。なぜかというと、人を疑っていると思われたくないから。なので私は、セルフレジの店員さんには「お客さんが操作している画面は見なくていいので、真ん中に立ってどんどん接客、困っている人がいたら声かけしてください」と指導します。すると、万引きって大幅に減るんです。地域の人には「犬の散歩やランニングのついでにホットスポットをまわってください。そして積極的に挨拶をしてください」と伝えます。監視状況を作るのではなく、人の目、そして人との交流が自然と生まれる環境を作ることを目指しています。

人と繋がるということ
大久保 これから、どのような社会になってほしいですか。
平野 PROSの活動では、わかりやすいから〈再犯防止〉と銘打っていますけど、私は目指すところは共生社会だと思っています。最初にも言いましたけど、出所者に「困ったら相談してね」とは伝えられるんだけど、本人は困っている自覚がないし、自分の状況を言語化できない。それで再犯してしまう。その溝を埋める必要があると思います。先日参加した学会で、精神科病院の身体拘束の話が出ました。患者さんの心配事とかを丁寧に時間をかけて聞くようにすると、拘束しなくて済むケースが多いそうなんです。ちゃんとコミュニケーションを取り、その人の背景を考えることが重要なんだと再認識しました。PROSの活動をしていると「なんで犯罪した人を支援するの?」「被害者がいるのに!」などと批判されることもあるんです。社会全体で意識を変えていく必要があるなと感じています。大久保先生は、犯罪が起こらない社会を作るために、なにが必要だと考えますか。
大久保 子どもが楽しく遊べるまち、夜ひとりで歩けるまち、それぞれのまちによって理想像は違うと思うんですけど、安全安心なまちづくりですね。言い換えると、犯罪しにくい環境づくり。それを機械ではなく、人の目で、人と人とのコミュニケーションの中で叶えることが大事なんだと思います。結局、人と、地域と繋がっていることが、犯罪を思い留まらせるのではないでしょうか。

教育学部 准教授
大久保 智生(おおくぼ ともお)
埼玉県熊谷市出身。早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。2006年4月より現職。万引き防止や地域防犯活動の研究に取り組む。

副理事
法学部教授・副学部長
平野 美紀(ひらの みき)
東京都中野区出身。慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。修士(法学)。国立精神・神経センター精神保健研究所研究員を経て、2006年4月より現職。終末期における患者の自己決定、犯罪者の処遇、被害者支援の研究に取り組む。