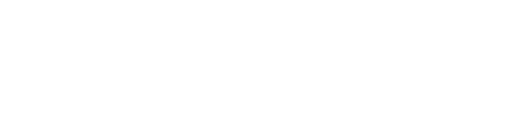DRI能力を育成するための基盤的教育
DRI能力を育成するための基盤的教育の目的は、より多くの学生にDRI能力を身につけてもらうことです。
授業紹介
ここでは、DRI能力育成科目の1つ「はじめて学ぶDRI」についてご紹介します。
-
はじめて学ぶDRI(全学共通科目・主題科目、第1クォーター、第3クォーター、1年生から受講可能)
「はじめて学ぶDRI」の授業の目的は、DRIを地域活性化にどのようにいかせるか、考え、説明することができるようになることです。この授業は、DRI教育の入門の役割を担い、DRIイノベーター養成プログラムの必修科目にもなっています。授業は、次のような流れで進んでいきます。シラバスはこちら (はじめて学ぶDRI【イ】)
シラバスはこちら (はじめて学ぶDRI【ロ】)- グループで地域課題を確認し、その解決策を考えます
- D・R・I それぞれの専門家が、D・R・I を地域活性化にどのようにいかせるかを説明します
- グループで、最初に考えた地域課題の解決策をDRIの観点から捉え直し、新たな解決策を考えます
2024年度の授業
受講者数は、1クォーターでは63人、3クォーターでは269人で、合計332人でした。今年度も人数にばらつきがあるものの、すべての学部から学生が参加していました。


グループワークの様子
各グループは、次のような地域課題に取り組みました。
人口減少を食い止めるには:香川県丸亀市/香川県で出産・子育てを安心してできる環境作り/若者の人口減少:香川県 /小豆島の交通改善/茨城県稲敷市の人口減少と過疎化について/人口減少対策:香川県/香川県塩江町の地域活性化/交通マナーの向上:反射材を普及させて/人口減少と若者の流出:香川県/離島振興:今、男木島はどうするべきか/結婚・出産・子育ての希望をかなえる:香川県さぬき市の現状から考える少子化対策とは/子育てしやすい地域社会にするために/出生率の低下と働き方改革
受講者の感想
- これまで自分が行ってきた解決策の導き出し方とは違ったDRIを活用した新たな導き出し方で地域課題について考えることで、新たな観点から地域課題をとらえ、これまでの考え方では導き出せなかったような解決策を考えられるようになったと思う。解決策を考える中では、グループ活動を通して自分では考え付かないような方法が出てくるため、自分が新たな価値観を吸収していくのを感じた。(教育学1年生)
- DRIの考え方をただ勉強するのではなくグループワークによって実践的に学ぶことができたので、実際にどのようにDRIを活用するのかよく理解することができた。また、各グループの発表やグループワークによって、他のメンバーやグループがどのようにDRIの考え方を受け止め、活用したのかが知ることができて視野を広く保つことができる授業だった。授業外でDRIそれぞれについて勉強することで、地域課題の解決にどうDRIを活かすのかゆっくり考えることができたのもよかった。発表に対する感想を参考によりDRIの考え方を現実の問題に対してうまく活用したい。(法学部1年生)
- 「はじめて学ぶDRI」を通して、人口減少や少子高齢化等が進行する現代社会には様々な課題があることを再認識することができ、これらの問題を解決したいという意欲が高まりました。人口減少や少子高齢化が現在、問題視されているのは認識していましたが、それらの事例や背景、歴史等などは全く知らなかったため、少し他人事として考えていたように思います。自分たちで問題の事例を探し、それらの問題について具体的に深く知っていくことで他人事として考えてはいけない、今の自分にできる精一杯のことを取り組もうと思えるようになりました。グループワークを通して意見を交換し合うことでも、それぞれの感性が違っているため、いろいろな意見が聞けてとても興味深かったです。パワーポイントの作成では、しっかり役割分担をし、計画的に進めることができました。デザイン思考やリスクマネジメント、インフォマティクスなど様々な観点から他者に対する共感を基盤とするデザイン思考を活用し、人々が共に幸福に生きる、安全安心な社会の実現を目指し、ビッグデータやICTをはじめとしたツールを駆使して物事を考える力をつけることができました。(医学部1年生)
過年度の授業はこちら
アセスメントテスト「DRI検定」
DRI教育の学習成果を可視化するための検定試験です。
アセスメントテストに関するQ&Aはこちら