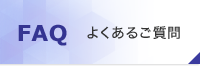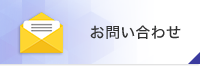防災・危機管理コース
「想定外」を防ぐ「発想力」。人の力と技術の力を組み合わせる「構想力」。さまざまな力を育み、これからの人類の安全・安心をデザインできる人材を育てます。

お知らせ
コースの概要
日本は地震や台風など大きな自然災害による被害を受けています。環境変化により従来にない大規模自然災害が発生する可能性が高まり、さらには社会システムの高度化・複雑化・国際化に伴い、これまでにない災害が発生する危険性も増大しています。いま、自然・人為的な災害に対応可能なレジリエント(しなやか)な社会の構築が求められています。
防災・危機管理コースは、自然災害などのリスク管理能力に長け、危機的状況においてもしなやかに対応できる人材を育成します。コース育成は「自然災害の軽減を目指す技術者」と「データサイエンスによる危機管理の専門家」の2つの柱から構成されます。
コースのカリキュラム
防災・危機管理コースカリキュラムは、大きく分けて3つのグループに分かれています。
防災・危機管理の考え方を学ぶコース独自の開講科目を中心に、建築・都市環境コースの開講科目や情報コースの開講科目など土木・建築工学や情報工学の基礎的科目を総合的に学ぶ構成です。

4年間の流れ
1年次は幸町キャンパスで、一般教養、デザイン思考やリスクマネジメントを学び、週1日ほどは林町キャンパスでプログラミングや工学系の基礎科目を学びます。4月には新入生歓迎イベントで、まちあるきなどがあります。
2年次からは林町キャンパス中心になり、2つの育成の柱に応じた学び方が選べます。コース共通の危機管理実践の基礎科目のほか、「自然災害の軽減を目指す技術者」は土木・建築系の科目を中心に、「データサイエンスによる危機管理の専門家」は情報工学系の科目を中心に学びます。また、防災士養成プログラムを通じた防災活動の実践などがあります。
3年次には研究室配属があり、各分野における専門・応用実践力を学びます。こうして身に着けた知識や技術は、4年次の卒業研究、防災・危機管理機関と連携した演習、地域の問題を解決する学外活動を通じて実践します。

卒業後の進路
卒業後の進路は、大学院修士課程でより高度な実践研究や、災害や危機に対して強い社会をデザインする技術者、データサイエンスによる危機管理の専門家、行政・企業などで危機管理を担当するマネージャーとしての活躍があげられます。
大学院で防災・危機管理について学ばれたい方は、以下の入試情報を確認ください。他大学からの進学、社会人入学も歓迎しています。
卒業後の進路(2025年4月現在)

主な就職先(五十音順、「株式会社」等は省略、下線は本コース卒業後に大学院 創発科学研究科に進学した学生)
| 建設業: | 奥村組、岳南建設、鹿島建設、川崎設備工業、鴻池組、中電工、ナイバ、西日本高速道路、四電工 他 |
| 製造業: | 朝日スチール工業、四国計測工業 他 |
| 電気・ガス: | 四国電力、四変テック 他 |
| 情報通信業: | イルグルム、STNet、NSソリューションズ関西、NTTデータ四国、MJC、ソフトバンク、東京電機産業、ネットワンシステムズ、富士通四国インフォテック、マイクロメイト岡山、メンバーズ、LIONA 他 |
| 卸売・小売業: | 石井事務機 他 |
| 不動産業: | ミサワホーム、あなぶき興産 他 |
| 学術研究、専門・技術サービス業: | アーク・ジオ・サポート、ウエスコ、応用地質、建設技術研究所、大日本ダイヤコンサルタント、中央コンサルタンツ、日本工営都市空間、日本ミクニヤ、四電技術コンサルタント、他 |
| サービス業: | 愛媛綜合警備保障、オフィス気象キャスター、原子力安全推進協会、日本赤十字社、パナソニック防災システムズ、晴れの国岡山農業協同組合 他 |
| 国家公務員: | 国土交通省近畿・四国・中国地方整備局、四国運輸局、経済産業省中国四国産業保安監督部、農林水産省中国四国農政局 他 |
| 地方公務員: | 愛媛県庁、岡山県庁、香川県庁、香川県警、倉敷市役所、坂出市役所、高松市役所、徳島市消防局、兵庫県庁、丸亀市役所 他 |
| 主担当教員 | |
|---|---|
| 磯打 千雅子(併任) | 研究室紹介・教員紹介 |
| 井面 仁志 | 研究室紹介・教員紹介 |
| 梶谷 義雄 | 研究室紹介・教員紹介 |
| 高橋 亨輔 | 研究室紹介・教員紹介 |
| 竹之内 健介 | 研究室紹介・教員紹介 |
| 地元 孝輔 | 研究室紹介・教員紹介 |
| 野々村 敦子 | 研究室紹介・教員紹介 |
*****
防災・危機管理コースには2つの履修モデルがあり、建築・都市環境コースや情報コースなどで開講されている科目を履修できます。関連するコースにおいて行われている教育・研究については、下記をご参照ください。
造形・メディアデザインコース
履修可能科目:Webシステム開発、線形計画法、非線形計画法など
建築・都市環境コース
履修可能科目:構造力学Ⅰ、土質力学Ⅰ、水理学Ⅰ、測量学など
情報コース
履修可能科目:インターネットⅠ、データベース、ソフトウェア工学など
人工知能・通信ネットワークコース
履修可能科目:情報理論、ビッグデータ解析など