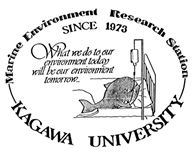 |
発行 2010年5月
香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション
香川県木田郡庵治町鎌野4511-15
TEL/FAX:087-871-3001 |
 |
 |
 |
| 2009年度 香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション 教育・研究活動と地域貢献事業 |
| ■2009年度 庵治マリンステーションスタッフ |
瀬戸内圏研究センター長 本城 凡夫
施 設 長 多田 邦尚 (農学部 教授)
施設主任 一見 和彦 (浅海域環境実験実習施設 准教授)
浜垣 孝司 (浅海域環境実験実習施設 技術専門職員)
関係教官 山田 佳裕 (農学部 准教授)
末永 慶寛 (工学部 准教授) |
| ■庵治マリンステーションに関わる新任教員・技術職員のお知らせ(2010年4月1日着任) |
 |
山口 一岩(Hitomi Yamaguchi)
農学部助教
農学部の一員に加わった山口と申します。これまで各地を転々としており、香川県には人生7回目の引っ越しでまず1回目の縁が出来ました。香川を離れてからしばらく経た今回、12回目の引越しで再び戻ってくることになりました。これまでプランクトンのような流浪生活を送ってきましたが、この縁を大切にし、ここに着底したいと望んでいます。マリンステーション面前の瀬戸内海から、色々なことを教えてもらえるように努める所存です。
それには皆さんの協力が欠かせません。どうぞよろしくお願いします。 |
|
 |
 |
 |
岸本 浩二(Koji Kishimoto)
庵治マリンステーション技術職員
この度、瀬戸内圏研究センター技術職員として庵治マリンステーションに着任いたしました岸本浩二と申します。これまで瀬戸内海の海洋生物や水産関連の仕事に従事してまいりましたが、これよりマリンステーションの管理と2隻の海洋調査船の船長として誠心誠意取り組む所存ですので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。 |
|
 |
 |
|
| 小型調査船「ノープリウスⅡ」を配備しました |
| 海洋調査船「カラヌスⅢ」の弟分として、海面養殖場周辺や干潟域など浅瀬のフィールド観測に活躍していた「ノープリウス」が、昨年度、「ノープリウスⅡ」として更新されました。搭載定員数も増え、船足も速くなった上(23ノット以上)、走行しながら水質をモニターできるハイテク機器も搭載されています。今後も質の高い教育・研究にノープリウスⅡを活用していきます(ページ最下部参照)。 |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2009年度に当施設が行った教育・研究活動と主な地域貢献事業についてご紹介いたします。 |
 |
| ■教育・研究活動 |
【教育(卒業・修士・博士論文研究を除く)】
5月20日 農学部応用生物科学・実習(1年生対象)
5月27日 農学部応用生物科学・実習(1年生対象)
8月 3日 農学部応用生物科学実験・実習
~7日 (生物資源環境化学実験Ⅱ 海洋環境実験・実習:3年生対象)
8月17日 生物学A(全学対象) |
 |
【博士論文研究: 愛媛大学大学院連合農学研究科・香川大学大学院工学研究科】
・Interactions between environmental condition and phytoplankton growth in eutrophic coastal water
生産環境学専攻 Suksomjit Marut (多田研究室)
・FRP炭化材を用いた海域環境改善技術に関する研究
安全システム建設工学専攻 明田定満(末永研究室) |
 |
【修士論文研究:香川大学大学院農学研究科・工学研究科】
・瀬戸内海東部海域の水塊構造における物理化学的・生物学的特徴に関する研究
生物資源生産学専攻 林 廣樹(一見研究室)
・瀬戸内海東部海域のアマモ(Zostera marina L.)の増殖特性に関する研究
生物資源生産学専攻 松野美穂(多田研究室)
・干潟食物連鎖系におけるタンパク質の質的変化に関する研究
生物資源生産学専攻 中野可織(多田研究室) |
 |
【卒業論文研究:農学部生命機能科学科・安全システム建設工学科】
・感潮域における懸濁粒子および栄養塩類の挙動について
萱野由香利(一見研究室)
・干潟生態系における鳥類のインパクト
小柳稔法(一見研究室)
・干潟域における植物色素群の濃度変動と組成について
東薗圭吾(一見研究室)
・栄養塩組成の変化が珪藻類の増殖に及ぼす影響
小竹秀明(多田研究室)
・魚類養殖(種苗生産)の閉鎖系循環飼育水槽における黄色物質の特性
中岡雅倫(多田研究室)
・堆積物表層における底生微細藻類の増殖とバクテリアによる分解
鹿摩賢士(多田研究室)
・流域にため池の多い河川における懸濁態有機物の起源
福田竜也(山田研究室)
・貯水池の影響の大きな河川における溶存有機物の動態
児玉政志(山田研究室)
・吉野川流域における河川水のトレーサビリティに関する研究
瀧本翔太(山田研究室)
・中小河川の有機物動態に及ぼす貯水池の影響
矢野昇宏(山田研究室)
・離岸堤設置にともなうアマモ場造成に関する研究
小枩裕典(末永研究室)
・波浪エネルギー吸収型動揺抑制技術に関する研究
樋口 輝(末永研究室)
・産業副産物を利用した水質・底質改善技術に関する研究
塚本博史(末永研究室) |
| ■2009年度 庵治マリンステーションに関わる研究業績 |
【学術論文】
●佐々木智史・宮川昌志・神田優・阿部昌明・山岡耕作・末永慶寛:瀬戸内海伊吹島におけるキジハタ放流人工種苗と天然当歳魚の生態.生態工学会,Journal of Eco-Engineering,20(1),15-26(2009).
●山田佳裕・三戸勇吾・中島沙知・小笠原貴子:しろかき後の強制落水によって排出される窒素の生物地球化学的変化.香川大学農学部学術報告,61,35-38(2009).
●小野哲・多田邦尚・一見和彦:大型珪藻Coscinodiscus wailesii の沈降に伴う生元素の鉛直輸送と沿岸海域の栄養塩環境への影響.沿岸海洋研究,46,153-160(2009).
●Loassachan, N., Ichimi, K. and Tada, K.: Evidence of Microphytobenthic Roles on Coastal Shallow Water of the Seto Inland Sea, Japan. Journal of Oceanography, 65, 361-372 (2009).
●Ohta, H., Ueda, T., Suenaga, Y., Tamura, T., Ichimi, K. and Tada, K.: Movement of Sand Particles from Sand Mining Area to Plant Bed, PACON International, Recent Advances in Marine Science and Technology 2008, 1-7 (2009).
●多田邦尚・門谷 茂・Veeraporn Suksomjit・広瀬敏一・一見和彦:ハマチ(Seriola quinqueradiata)養殖場における沈降粒子束.日本水産学会誌,75,383-389(2009).
●山田達夫・橋本俊也・末永慶寛・一見和彦・多田邦尚:魚類(ハマチ)養殖場における残餌の沈降と拡散.日本水産学会誌,75,666-673(2009).
●多田邦尚・一見和彦:浅海域海底の微細藻類の活性と底泥からの栄養塩の溶出.沿岸海洋研究,47,29-37(2009).
●Suksomjit, M., Tada, K., Ichimi, K., and Montani, S.: High tolerance of phytoplankton for extremely high ammonium concentrations in the eutrophic coastal water of Dokai Bay (Japan). La mer, 47, 75-88 (2009).
●Tada, K., Suksomjit, M., Ichimi, K., Funaki, Y., Montani, S., Yamada, M. and Harrison, P.J. : Diatoms Grow Faster Using Ammonium in Rapidy Flushed Eutrophic Dokai Bay, Japan. Journal of Oceanography, 65, 885-891 (2009).
●Suksomjit, M., Ichimi, K., Hamada, K., Yamada, Y., Tada, K. and Harrrison, P.J.: Ammonium accelerates the growth rate of Skeletonema spp. in the phytoplankton assemblage in a heavily eutrophic embayment, Dokai Bay, Japan.: La mer, 47, 89-101 (2009).
●Suksomjit, M., Nagao, S., Ichimi, K., Yamada, Y., and Tada, K.: Variation of Dissolved Organic Matter and Fluorescence Characteristics Before, During and After Phytoplankton Bloom Journal of Oceanography, 65, 835 -846 (2009).
●Miyagawa, M., Tochino, M., Aminaka, M., Fujiwara, M., Suenaga, Y. and Kakegawa, H.: Research on the Safer Shelter for Released Fish Juveniles. PACON International, Recent Advances in Marine Science and Technology 2008, 8-14 (2009).
●Akeda, S., Suenaga, Y., Yasuoka, K., Hoshino, T. and Kakegawa, H.: Application of Carbonized Waste FRP Fishing Boats for Artificial Reef. PACON International, Recent Advances in Marine Science and Technology 2008, 15-22 (2009).
●Akeda, S., Suenaga, Y. and Miyagawa, M.: Field Actual Proof on the Enhancement of Food Organisms Using FRP Carbide. The International Association of Hydraulic Engineering and Research, Proceedings of XXXIII IAHR Congress (CD ROM), (2009).
●明田定満・末永慶寛・松島学・居駒知樹:FRP漁船の寿命と耐用年数.日本沿岸域学会論文集,22,77-88(2009).
●Nishikawa, T., Hori, Y., Nagai, S., Miyahara, K., Nakamura, Y., Harada, K., Tanda, M., Manabe, T. and Tada, K.: Nutrient and Phytoplankton Dynamics in Harima-Nada, Eastern Seto Inland Sea, Japan During a 35 Year Period from 1973 to 2007. Estuaries and Coast, 33, 417-427 (2010). |
 |
【学会講演等】
●多田邦尚・中野可織・一見和彦:干潟の食物連鎖系におけるタンパク質の栄養価.2009年度日本海洋学会秋季大会(於京都),講演要旨集p88
●多田邦尚・松野美穂・一見和彦:アマモの栄養塩取り込みについて.2009年度日本海洋学会秋季大会(於京都),講演要旨集p91
●多田邦尚・朝日俊雄・一見和彦:河口干潟域における懸濁態リンの挙動.2009年度日本海洋学会秋季大会(於京都),講演要旨集p90
●林廣樹・一見和彦・多田邦尚:瀬戸内海東部海域における生物・化学環境の季節的特徴.2009年度日本海洋学会秋季大会(於京都),講演要旨集p91
●山田達夫・多田邦尚・一見和彦:魚類養殖場におけるCOD増加について.2009年度日本海洋学会秋季大会(於京都),講演要旨集p92
●西川哲也・堀豊・長井敏・宮原一隆・原田和弘・中村行延・多田邦尚・今井一郎:播磨灘におけるノリ色落ち原因珪藻Eucampia zodiacus個体群の長期変動と環境要因:35年間のモニタリング.2009年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会(於函館),講演要旨集p19
●日髙朋子・大坪繭子・山田真知子・一見和彦・多田邦尚:西日本の3階域の海底泥から発芽した海産珪藻Skeletonema属の種多様性.2009年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会(於函館),講演要旨集p23
●河口真弓・大坪繭子・山田真知子・香月絵里・帰山秀樹・多田邦尚・一見和彦:洞海湾で分離されたSkeletonema属の生理生態特性研究Ⅰ 季節的消長と種多様性.2009年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会(於函館),講演要旨集p24
●帰山秀樹・河口真弓・山田真知子・香月絵里・一見和彦・多田邦尚:洞海湾で分離されたSkeletonema属の生理生態特性研究Ⅱ. Skeletonema属の増殖に及ぼす温度および光強度の影響.2009年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会(於函館),講演要旨集p25
●松野美穂・多田邦尚・一見和彦:アマモ種子の発芽条件の検討.2009年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会(於函館),講演要旨集p80
●一見和彦・李仁恵・山本昭憲・多田邦尚:干潟域から分離された高増殖能力を持つ微細藻類について.2009年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会(於函館),講演要旨集p122
●桑江朝比呂・三好英一・細川真也・一見和彦:小型シギ類における餌資源としてのバイオフィルムの重要性.2009年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会(於函館),講演要旨集p87
●一見和彦・松尾武芳・桑江朝比呂・柴沼成一郎・門谷茂:鳥類による底生生物の摂取量-風蓮湖に渡来するスズガモおよびオオハクチョウの事例-.2009年日本ベントス学会・日本プランクトン学会合同大会(於函館),講演要旨集p88
●Sadamitsu Akeda, Yoshihiro Suenaga, Masashi Miyagawa: Field Actual Proof on the Enhancement of Food Organisms Using FRP Carbide. The International Association of Hydraulic Engineering and Research, Proceedings of XXXIII IAHR Congress, Vancouver, Canada, Aug. 2009. |
 |
【学会賞受賞】
香川大学農学部卒業生(平成20年度愛媛大学連合大学院修了)の小野哲君が日本海洋学会沿岸海洋部会速水論文賞を受賞し、去る3月30日に東京海洋大学で開催された日本海洋学会において授与式が行われました。本賞は、2年に1度、学術雑誌「沿岸海洋研究」に掲載された論文の中からひとつ選ばれた優秀な論文の第1著者に対して授与されています。受賞対象となった論文は、下記の論文です。
『小野哲・多田邦尚・一見和彦:沿岸海洋研究, 46, 153-160 (2009) 「大型珪藻Coscinodiscus wailesii の沈降に伴う生元素の鉛直輸送と沿岸海域の栄養塩環境への影響」』
本論文は、多田研究室で愛媛大学連合大学院農学研究科に在学中の小野君が投稿したものです。 |
| 小野君は、当時の浅海域環境実験実習施設(現瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション)の調査船カラヌスⅢ、ノープリウス(現在はノープリウスⅡ)を用いて精力的に調査を行い、冬季に大増殖する大型珪藻Coscinodiscus wailesii が現場の海域環境に及ぼしている影響について明らかにしました。本受賞は、瀬戸内海に代表される閉鎖性水域の環境問題に対し、物の動きを大きく捉える物質循環に根差した研究内容が評価されたといえます。なお小野君は、2003年にタイ王国で開催された6th International Conference on the Environmental Management of Enclosed Coastal Seas(第6回世界閉鎖性海域環境保全会議)においてもベストポスター賞を受賞しており、本施設で実施した研究が二つの大きな賞を受賞したことになります。 |
|
 |
 |
|
| ■庵治マリンステーションセミナー |
2009年5月26-27日
「沿岸海域の環境と植物プランクトン」(Paul J. Harrison教授を囲んだ研究集会)
【5月26日】
1. 干潟域の底生微細藻類の増殖とその生産環境
一見和彦(香川大学瀬戸内圏研究センター)
2. 北九州市・洞海湾における植物プランクトン組成の変化
山田真知子(福岡女子大学人間環境学部)
3. 北九州市・洞海湾における栄養塩濃度の減少と植物プランクトン量の変動
濱田健一郎(北九州市立大学アクア研究センター)
4. 植物プランクトンの細胞内リンの形態
帰山秀樹(香川大学農学部)
5. 瀬戸内海東部海域における植物プランクトン群集の長期変動
西川哲也(兵庫県立農林水産技術総合センター但馬水産技術センター)
6. 瀬戸内海播磨灘における植物プランクトンの季節変動と栄養塩環境
多田邦尚(香川大学農学部)
7. 総合討論
【5月27日】
特別講演:「植物プランクトンの増殖と栄養塩要求」
Paul. J Harrison教授(ブリティッシュコロンビア大学・香港科学技術大学)
2009年6月16日
演題:森-里-海 連環学
演者:山下 洋 教授(京都大学フィールド科学教育研究センター 舞鶴水産実験所) |
| ■地域貢献事業 |
2009年
・7月 3日 直島小学校環境学習(講師として一見准教授が参加)
・7月28日 干潟ウォッチング(新川・春日川河口干潟&庵治マリンステーション)
(香川県・エコライフかがわ推進会議)
・8月13日 第5回香川自然博物館-干潟と磯の生き物ウォッチング-
(於 有明浜:講師として多田教授、一見准教授が参加)
・9月16日 香川大学シニアカレッジ2009:浅海体験実習
(香川大学・JTB) |
| ■国際貢献事業 |
・アジア若手研究者交流プログラムにより、沿岸堆積物における生元素循環の研究のため、タイ王国チュラロンコン
大学理学部Thlisongouthai講師が40日間滞在
・タイ王国カセサート大学水産学部・チュラロンコン大学理学部と日本産・タイ産夜光虫に関する共同研究のため、
5月にMeksumpan準教授(カセサート大学水産学部)、Lirdwitayaprasit準教授(チュラロンコン大学理学部)が
滞在
・香港工科大学(前ブリティッシュ・コロンビア大学)のP. J. Harrison 教授をお招きしてワークショップを開催(7月)
・日本産・タイ産夜光虫に関する共同研究のため、瀬戸内圏研究センター・副センター長の多田邦尚教授が、3月に
タイ王国カセサート大学水産学部・チュラロンコン大学理学部を訪問 |
| ■その他 |
2010年
・3月19日 瀬戸内圏研究センター研究プロジェクトシンポジウム(於サンポート高松)
第1部 研究報告「干潟を含めた浅海域の生態系研究」
多田邦尚 瀬戸内圏研究センター副センター長 |
 |
(写真左)7月に開催したワークショップ。Harrison教授による基調講演の様子。
(写真右)Harrison教授ご夫妻とワークショップ参加者との懇親会にて。 |
 |
|
| ■インタラクティブコーナー |
皆様と自然科学の研究者とで創るコーナーです。
皆様がこの通信の中で興味を持たれたこと、また疑問に思われたこと、身近な自然の中で不思議に感じられたことがありましたらどしどしお便りください。このコーナーで取り上げさせていただいて、読者の方々の自然に関する興味や知識を深めることが出来たらと思っています。特に投稿規程はありません。お便りお待ちしています。 |
|
投稿先:〒761-0130 香川県木田郡庵治町鎌野4511-15
香川大学瀬戸内圏研究センター 庵治マリンステーション 一見 和彦 宛
電子メール:ichimi@ag.kagawa-u.ac.jp
庵治マリンステーションホームページ http://www.kagawa-u.ac.jp/setouchi/index.html
◆浅海環境通信のバックナンバーも上記ホームページからご覧いただけます。
|
編集:庵治マリンステーション利用者グループ |
 |
小型調査船ノープリウスです。平成21年度でノープリウスⅡ世に引き継ぐことになりました。 |
 |
| ▲ 上に戻る |
 |
|